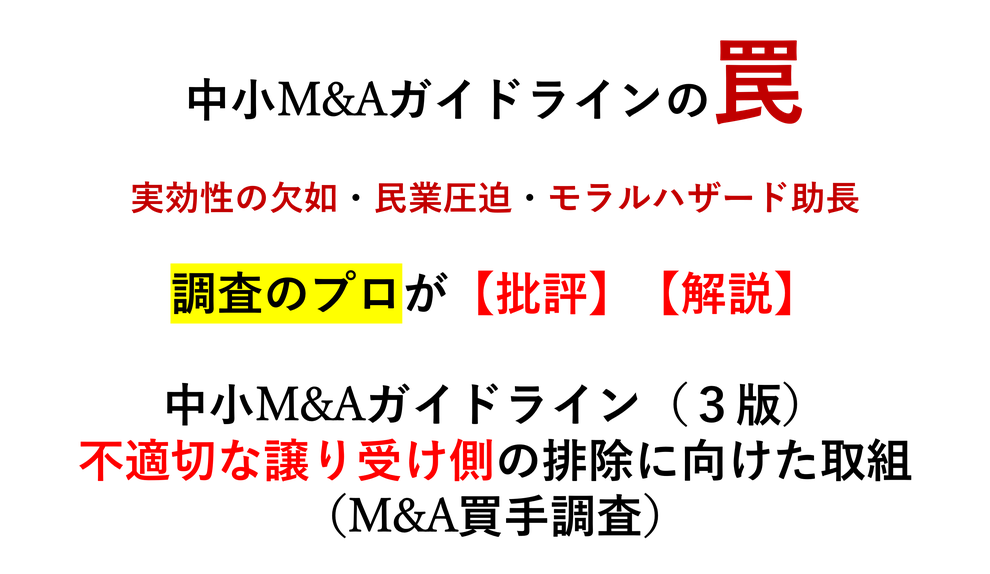
以下は、『中小 M&A ガイドライン(第3版)』における『不適切な譲り受け側の排除に向けた取組』(M&Aにおける悪質な買手を排除するための調査)について、反社会的勢力に関わる信用調査会社である弊社代表が思うところを記した批評および解説である。吸血型M&Aとも称される悪質な買い手によるM&Aへの実務対応の一助となれば幸いである。
それにしても、中小企業庁(中企庁)の策定したガイドラインは、本格的な詐欺師に対する対策としてはその実効性に疑問があるのみならず、文言や意図も曖昧であるため、このような散文に実質的に縛られるM&A業者(仲介・FA)は気の毒に思う。偏向報道にあおられ弱者救済の名目で民間企業の取引審査のあり方に介入する国(血税の使われ方)に対する警鐘の意味も込めている。
**で囲われた黒字は『中小 M&A ガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-』の『6不適切な譲り受け側の排除に向けた取組 』(100P ~103P)からの引用部分であり、青字は筆者の批評および解説部分である。
*******************************************************
6 不適切な譲り受け側の排除に向けた取組
両当事者間で締結された最終契約における譲渡額の支払をはじめとした譲り渡し側・譲り受け側双方が負う義務の確実な履行は M&A の成立の上での前提であり、その適切な履行の実現を担保していくことが重要である。
一方、M&A に関連して違法と疑われる行為(例えば、M&A の成立後に譲り渡し側の資金を個人口座に送金する等)、最終契約に定めた義務の不履行・M&A 実施後に当事者双方が M&A 実施前に想定していた内容と異なる事業運営(例えば、譲り渡し側の経営者保証を譲り受け側に移行させる想定であったにもかかわらず移行しない等)を行う譲り受け側の存在が指摘されている。こうした不適切な譲り受け側は中小 M&A の市場から排除していく必要があり、M&A の成立に向けた支援を行う仲介者・FA による譲り受け側に係る情報の確認の実施が対策として考えられる。当該確認には限界もあり、譲り受け側の信用を保証するレベルでの実施は難しい側面もあるが、不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から、仲介者・FA(M&A プラットフォーマーを含む。以下(1)~(3)において同じ。)には、少なくとも以下の取組が求められる。
*******************************************************
【批評】
- 文中に❝当該確認には限界もあり、譲り受け側の信用を保証するレベルでの実施は難しい❞とある一方で、❝義務の確実な履行はM&Aの成立の上での前提であり、その適切な履行の実現を担保していくことが重要❞とある。義務の実現の担保と信用を保証するレベルでの確認の実施の強弱と文章の整合性が理解不能である。常識的には義務の履行を確実に担保することは信用を保証するレベルと同義である。一体、何を目的としているのか理解に苦しむ。
- 仲介者とFAが一緒にくくられている粗雑さ。買手側のFAの場合は、当然、買手FAとして調査した買手の不適切性について、何ら契約関係のない売手側には伝達する義務(根拠)がないはずであるが、以下のガイドラインでは仲介者もFAも区別なく売手に対する開示を実施しなければならないと読めるような記述がされている。このような推敲を手抜きしたとも捉えられるガイドライン(税金を使って作成!)で民業を圧迫するのは勘弁願いたい。
*******************************************************
(1) 譲り受け側に対する調査
仲介者・FA は、譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査を実施することが求められる。詳細な調査の実施内容については、譲り受け側の財務状況及び事業実態の確認、譲り受け側(代表者、役員及び株主等の関係者を含む。)の反社会的勢力への該当性や過去に M&A に関するトラブルを生じさせたかといったコンプライアンス面での確認が想定され、これらの観点から適切に調査を実施することが求められる。特に財務状況については、想定される程度の譲渡対価を調達可能であるかといった観点や M&A の実施後に対象事業を継続して運営できる状況にあるかといった観点からの適切な確認が必要である。
*******************************************************
【批評】
- 補助金の不正受給や官民ファンドで失敗している経済産業省(およびその傘下の中企庁)が、まず自ら、補助金の受給者が補助金を有効に使う意思・能力を有しているか審査する能力を備えるべきである。他人のカネだと脇が甘くなるのは官民共通だが、絵空事に釣られて血税を拠出した官民ファンドが有効に資金を活用できる運営能力を有しているか、まず自ら調査する能力を備えるべきだ。いいかげんな審査で膨大な血税を詐欺師に垂れ流してきたことは棚に上げて、民間企業への偏向的な政策に血税を使うのは勘弁願いたい。
******************************************************
調査のタイミングとしては、譲り受け側との仲介契約・FA 契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に加え、M&A のプロセスが進捗する過程でも適切に必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り受け側について十分に確認することが重要である。また、調査の方法としては、譲り受け側の税務申告書や商業登記簿の確認、これらに記載のある代表者、役員及び株主等の関係者も含めたコンプライアンスチェックが想定される。もっとも、譲り受け側の信頼性や譲り渡し側の財務状況等によって必要となる調査の粒度は異なると考えられる。特に、譲り渡し側が債務超過の場合等、M&A の成立において譲り受け側の信用が特に重要となるケースにおいては特に慎重な調査の実施が必要であり、この場合においては譲り受け側の財務状況について、少なくとも決算公告や税務申告書の確認により適切な確認を実施することが求められる。一方で、保証債務が移行せず、簿外債務を遮断できる事業譲渡の場合等、取引の形態によっては調査の必要性が低い場合も想定される。
*******************************************************
【批評】【解説】
- 譲り受け側への十分な確認は、最終契約の締結(前)までであれば、各社の実務上の都合で実現可能なタイミングで実施すればよいと解釈できる。もちろん序盤からしっかりと確認するに越したことはなく、トップ面談まで実施したあとにようやく買手を調査して、その結果、不適切(悪質)だったと判明した場合の仲介者とFAの信頼失墜は計り知れない。実務上の都合とレピュテーションとの天秤で審査フローを構築するべきである。ご相談にはいつでも乗りますのでお気軽にお問い合わせください。
- ❝譲り受け側の信頼性や譲り渡し側の財務状況等によって必要となる調査の粒度は異なる❞の一文は重要である。リスクベースアプローチによるメリハリ付けを実施すべきであると読める。リスクの低い相手や案件に対しては限定的な調査で足りるということだ。しかし、何をもって「譲り受け側の信頼性」「譲り渡し側の財務状況等」とするかは、各社で決めなければならない。恣意性を排除するため一定の基準を設けつつ、個別案件において都度適切な判断を行う体制を整えなければならない。この辺りの審査体制の構築についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。
- (譲り渡し側が債務超過等の場合)譲り受け側の財務状況の調査として、❝少なくとも決算公告や税務申告書の確認により適切な確認を実施することが求められる。❞とある。これは噴飯ものだ。決算公告とは、非大企業の場合、貸借対照表の公告(現預金の額などは不記載。流動・固定の資産/負債のみ記載の大雑把な財務情報)に過ぎない一方、税務申告書は最高レベルの粒度の資料である。これを並列的に記述している意味が不明である。少なくとも~という最低条件を規定するのに、粒度の著しく低い『決算公告』と『税務申告書』を併記している違和感を抱くのは私だけではないだろう。審査のエキスパートであれば苦笑せざるを得ない一文だ。
- このようないい加減な散文によって実質的に規制されるM&A業者は気の毒だ。個人的にはこのガイドラインが適用されるM&A業界の事業環境は急激に悪化したと仮説している。後述するようにこのガイドラインに基づく調査の詐欺検出の実効性に疑義がある一方、このような曖昧な規定ではM&A業者が萎縮するばかりであり(私なら怖くてビジネスできない)、社会課題となっている事業承継が停滞しかねない。
- そもそも事業承継の本質は、一面では債務承継にすぎず、銀行の尻拭いを一般のM&A業者が負わされているといった見方もできよう。今般のガイドラインでは経営者の連帯保証の解除について銀行への綿密な確認が必要となるが、銀行の手のひらの上で右往左往するビジネスに魅力を感じない。銀行自体が(利益相反疑義をものともせず)事業承継ファンドを立ち上げ、うまみのある取引先同士は自分たちがマッチング(M&A)してフィーを得る一方、銀行から見て魅力のない債務超過先や懸念先が、一般のM&A業者が扱うマーケット(M&Aのマッチングサイト等を含む)に放出されるだけの酷い業界に成り下がってしまうのではないか。債務超過企業にはハイエナのような詐欺師が昔からうろつく。そうした危険なマーケットにおいて、曖昧かつ非現実的なガイドラインを押し付けられるM&A業者は本当に気の毒だ。リスクとリターンが見合わない。まじめな業者であっても事業継続を断念する事態が生じかねない。
- 一般社団法人M&A支援機関協会(旧M&A仲介協会)なる業界団体が存在するが、実質的規制庁である中企庁によるこのような横暴(推敲の足りない曖昧な散文で民業を圧迫)に対して毅然とした対応をする気骨ある組織なのだろうか。ただ単に上から降りてきたものを会員に押し付けるだけの傀儡的な組織なのだろうか。短絡的に資格制度を作ることで中企庁の利権団体と化さないか。省庁と関係の深い民間団体は天下り含め多角的に注視したい。
- ❝保証債務が移行せず、簿外債務を遮断できる事業譲渡の場合等、取引の形態によっては調査の必要性が低い場合も想定される。❞とあるが、これでは事業承継であればリスクが低いと読めてしまう。規制庁自らリスクを弛緩させる一文を加えたのが理解不能だ。事業承継であっても預金口座が移管する場合もあるし(預金口座だけ収奪して逃亡するなど吸血型事業譲渡)、何より雇用の移動が伴う場合は、譲り受け側について株式譲渡と同等レベルの確認は実施すべきだ。保証債務だけがリスクファクターではない。もう少し推敲してからガイドラインを示してほしい。ミスリードを招くだけだ。
*******************************************************
いずれにせよ、仲介者・FA は、個別の案件ごとにおける必要性を踏まえ、譲り受け側の調査の実施方法や調査の範囲、実施主体等について以下の表に基づき検討・実施する必要がある。その上で、依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に、譲り受け側の調査の概要について、説明しなければならない。
具体的には、仲介者・FA は以下の表の「調査項目」ごとに、実施する調査の内容を検討し、依頼者への説明を行う必要がある(以下の表の「調査の概要」の列には例を記載。)。また、説明を踏まえ、調査の内容について譲り渡し側から依頼があれば見直しを検討しなければならない。

(上表はガイドライン本文ではなく、『中小M&Aガイドライン改訂(第3版)に関する概要資料』(2024年8月中小企業庁財務課)22ページより転載/https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002-ar.pdf)
*******************************************************
【批評】【解説】
- 上表の通りの調査を実施しても、今般の「吸血型M&A」の代表格である某社のような詐欺会社を具体的にどのように見抜けるか一般事業者には判然としない。弊社は専門調査会社(反社や詐欺専門)であるので、某社について同社設立時点の情報だけで、10分以内に取引を遮断すべきであるとの確たる情報を検出して判定を出せるノウハウを有している。その手法は基本的なものであるが、中企庁の示す上表には全くその手法が全く記されていない。およそ信用調査のプロが策定したとは思えない調査内容だ。ガイドライン第3版の委員に調査会社の人間が誰も入っていないのがその証拠だ。もっとも一般の信用調査会社では見抜くのは難しいだろう(一部調査会社では検知不能だったようだ)。
- 「コンプライアンスに関する調査」において❝反社会的勢力への該当性❞と記していること自体で素人丸出しだ。該当する人物をフロントに出す間抜けな詐欺師がいるだろうか。現代の反社チェック実務では、該当性のみならず「関係性」の検出が主テーマとなっていることを知らないのだろうか。税金を使ってミスリードするのは勘弁願いたい。
- そもそも審査実務において手の内を公にすることはナンセンスだ。審査において、どんな資料をどのように調べるのかは出来るだけ秘密にしておくべきなのであるが、上表のような調査内容をオープンにするのはナンセンスだ。
- 例えば「最終契約の実行可能性の調査」で記されている「預金通帳」だ。これを予め調査すると公言する意味が不明である(中企庁が例示しているということは代表的な調査手法として推奨しているのだろう)。預金通帳のコピーやインターネットバンキングの画面コピーの改ざんなど詐欺師にとってお手の物だ。こうした帳票は詐欺師が対策する余地をなくすために急に徴求するのが調査のセオリーだ。事務所に訪れた時などに、ふいに見せてもらうものだ。不動産取引において地面師詐欺が跋扈するのは、実務的に必要な確認書類が周知となってしまっているからだ。詐欺師に事前に対策されてしまうからだ。このガイドラインは何を目的にしているのだろう。今般問題を起こした一部の吸血型M&A詐欺の背後人脈を調べていないのだろうか。愕然とするほかない。協会は中企庁にクレームすべきだ。
- そもそも民間の取引審査において相手から「預金通帳」まで徴求することは難しい場合が多い。例えば東証プライム上場企業やその子会社に対し「預金通帳を見せてください」などと言っても無理だろう。中小企業レベルでも(取引銀行全ての)預金通帳を見せることなど税務署でもない限り拒むだろう。
- 重要事項説明において確認の実行可能性が未知数の預金通帳を「調査します」と確約的に売手に説明するのはリスクだ。売手としてみたら、M&A業者(仲介者・FA)が預金通帳まで確認してくれるから安心だと錯覚してしまう(リスク弛緩)。ガイドラインでは示されてないが、一定の属性の企業に対しては、示した調査内容が限定的となる旨を付記すべきだろう。できない確認をできると説明することは嘘をつくことになるし、リテラシーの低い売手の中小零細経営者に誤解されトラブルが生じるからだ。このままだと中企庁はM&A仲介・FAに嘘をつけと言っているに等しい。
- そもそもの大前提だが、買手の預金通帳まで確認すべきなのは売手自らだ。売手の自らの責任において買手に預金通帳を見せてもらうようネゴシエーションするのが本来の姿だ。保証を外すのは売手なのだから、カネを借りた金融機関に「資金力のある買手です。だから保証をこの人に移してください」と説明するのは売手!!あなたなのですよ。何十年も経営してきて、カネを借りる、保証を入れる、それを差し替えることの重大性を認識していないのは経営者として失格だ。そうした不勉強な経営者のせいで中企庁が税金を投じてこのようなガイドラインを作らざるを得ないのだ。偏った「弱者救済」報道にあおられ税金や官僚リソースが間違った方向に使われているように思える。
- 実務的にはガイドラインで示された5つの調査項目、すなわち「財務状況に関する調査」「コンプライアンスに関する調査」「事業実態に関する調査」「最終契約の実行可能性の調査」「その他の調査」の項目自体はマストで設定するとして、その具体的な内容はタイミングも含めて各社で決めて実施していく。例示された内容では上記の通り、不具合もあるため、トラブルが生じないような記載が望まれる。なによりガイドラインに示されない有効な調査手法について盛り込みたい。これからの時代、審査力こそM&A業者の競争要素だからだ。その辺りの相談もお気軽にお問い合わせください。
*******************************************************
また、その方法を変更する場合には変更の内容を理由とともに説明しなければならない。さらに、遅くとも最終契約の締結前までに、調査を実施し、その結果リスク事項を検出した場合には、開示可能な範囲で調査の結果を譲り渡し側に報告し、取引実行の可否や最終契約に規定すべき条項の内容を協議しなければならない。
(2) 不適切な行為に係る情報を取得した場合の対応
仲介者・FA は、過去に支援を行った譲り受け側についての情報提供や(3)の業界内での情報共有の仕組み等により最終契約の不履行等の不適切な譲り受け側に係る情報を取得した場合には、当該情報を担当者レベルに留めず、組織的に共有し、当該譲り受け側に対するマッチング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築
しなければならない。
当該譲り受け側への新たな支援の実施については、取得した情報の内容の精査及び同様の行為による譲り渡し側への不利益の考慮により慎重に検討の上、仮に実施する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)によらなければならない。
なお、仲介者にあっては、本章Ⅱ5「仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策」に記載のとおり、両当事者間における利益が対立する事項(一方当事者にとっての有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を各当事者に対し、適時に明示的に開示することを求めている。このため、譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に開示することが求められる。
*******************************************************
【批評】
- 買手に対する調査の結果を、開示可能な範囲内で売手(譲り渡し側)に報告せよ、とのことである。実際に開示可能なことは限定されるだろう。なぜなら反社会的勢力との関係性を含むリスク情報というのは「見立て」(判断)であり、そのまま伝達すると名誉棄損(人権侵害)や信用棄損に繋がる恐れがあるからだ。信用調査とその結果は、本来、自社内のごく限定された必要最小限の範囲内で使用するのが大原則だ(名誉棄損における拡散性の遮断)。情報を提供する調査会社も、第三者に流出しかねない相手に踏み込んだ調査を報告することは嫌がるだろう。このような信用調査の原理原則を理解しない官僚様の規定したガイドラインに縛られるM&A業者は気の毒だ。
- 何度も繰り返すが、信用調査というのは自らの為だけに行うものだ。だから売手が自らの責任と費用で調査会社を起用し、M&Aに臨むべきなのだ。その費用が捻出できないならその時点でM&Aを実施する資格はないし、自分のやってきた経営は失敗だったと反省すべきであろう。
- M&A業者は自ら業者としての調査を実施するが、それとは別に、主人公たる売手自らもしっかりと買手を調べるべきだ。M&A業者が必要な調査を代行してくれると錯覚してはならない。中企庁のガイドラインは、こうした売手経営者のリスクマインドの弛緩を招いているように思える。
- 譲り渡し側への説明は非常にセンシティブな行為である。伝え方によってはトラブルが生じる。リスクとして検出した事象を組織的にどのように解釈し、それをどの程度まで売手に説明するかについては慎重な検討が必要である。この辺りの組織的なルール作りについてもお気軽にお問い合わせください。
*******************************************************
(3) 業界内での情報共有の仕組みの構築
(1)(2)の個社の取組に加え、さらに不適切な譲り受け側の排除を実行可能なものとしていくためには、業界内での情報共有の仕組みが求められる。具体的には、自らが支援した譲り受け側について、最終契約の不履行等の不適切な行為を働く者に係る情報を業界内で共有する仕組みの構築が期待される。
当該仕組みにおいては、情報共有の範囲内における情報管理を前提とした上で、可能な限り多くの仲介者・FA が参加し、仲介者・FA の組織内において適切に情報共有がなされることにより、中小 M&A 市場における信頼性を確保するための基盤として実効性のある形で浸透することが求められる。このため、仲介者・FA 等の支援機関にはこのような情報共有の仕組みに参加することによって、自らの支援の質、ひいては中小 M&A 市場の質の確保に努めることが強く望まれる。
また、仲介者・FA は、仲介契約・FA 契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プラットフォームへの登録前)に、このような業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)について、依頼者に対して説明しなければならない。
*******************************************************
【批評】
- このような絵空事の情報共有の仕組みは機能しないだろう。何をもって「不適切な譲り受け側」かの評価は一概ではない。貸金業者などのネットワークを模範にしていると考えられるが、「金融債務の不履行」という事実がはっきりする事象と「不適切な譲り受け側かどうか」の判定は、全く性質の異なるものだ。後者は「見立て」情報である故、それを共有し流布させることに名誉棄損(人権侵害)や信用棄損リスクが伴う。またこのようなネットワークがある業界に対し、反社調査を専門とするような調査会社は恐ろしくて情報提供ができない。かえって有用な情報の流通を妨げてしまう。税金を投入しながら何故このような貧弱かつ短絡的な発想に至るのか。中企庁は説明すべきだし、これを実施しようとする業界団体(M&A支援機関協会:旧仲介協会)は、会員の法的リスク(名誉棄損・信用棄損等)がクリアになるまで情報共有の仕組みのあり方について中企庁からの説明を求めるべきだ。
- M&A支援機関協会が不適切な譲り受け側事業者を共有する「特定事業者リスト」に係る運用を改定した。それによれば、エスクローの利用の推奨が義務化される(「M&A 対価の分割払いや退職慰労金の後払いをする場合、制度参加会員は、顧客に対しエスクローサービス活用を推奨する義務が生じます。」(『不適切な譲り受け側事業者を共有する「特定事業者リスト」を改訂』(M&A支援機関協会HPより)。
- なぜ一律にエスクローを推奨する義務を負わなければならないのか?エスクローは中小M&Aにとってコスト負担が大きいし、優良な買手もいる。エスクローを利用するかどうかは調査結果によるリスク判定や案件ごとの個別事情によるべきであり、一律にエスクローを推奨しなければならない理由は何か。同協会の協賛会員にエスクローサービスを提供する業者がいないか?会員各社はこの条文について利害関係や利益相反がないか本条文の設定経緯を十分に確認し、協会のやり方を監視すべきだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、不適切な譲り受け側に関する批評と解説でした。このような曖昧なガイドラインのせいで右往左往されているM&A業者様も多いでしょう。より踏み込んだ実務上の課題について知りたい方、あるいは中小M&Aガイドライン(3版)を踏まえた審査フローの再構築された業者さまはお気軽にご相談ください。
まだまだ『中小 M&A ガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-』には突っ込みどころがたくさんああります。血税を使ってまで(このようなガイドラインを策定してまで)、わきの甘い売手経営者を守る必要はどこにもありません。民間の取引審査のあり方に国が介入することの弊害は甚大です。経営者のリスクマインドを弛緩させ、ゾンビ企業を量産することになります。そうしたことを許容すると我々の税負担は底なしになります。自己責任原則という経営者の基本原理を蔑ろにした偏向報道にあおられ、弱者救済を名目とした正義感によって血税が浪費されています。取引の審査は民間企業の企業努力で切磋琢磨していくものです。審査力こそM&A業者の競争要素(差別化要素)であるべきです。
アクティブ株式会社 泉博伸
2025年3月17日
2025年4月2日追記
Copyright @ 2016 ACTIVE CORPORATION All Rights Reserved.

